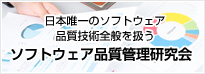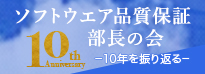| 研究コース1 | 研究コース2 | 研究コース3 | 研究コース4 | 研究コース5 | ||||
| 演習コースI | 演習コースII | 演習コースIII | 演習コースIV | 基礎コース |
|
研究コース1 「ソフトウェアプロセス評価・改善」 をおすすめいたします! |
|
研究コース2 「ソフトウェアレビュー」 をおすすめいたします! |
|
研究コース3 「ソフトウェアテスト」 をおすすめいたします! |
|
研究コース4 「アジャイルと品質」 をおすすめいたします! |
|
研究コース5 「人工知能とソフトウェア品質」 をおすすめいたします! |
|
演習コースI 「ソフトウェア工学の基礎」 をおすすめいたします! |
|
演習コースII 「ソフトウェアメトリクス」 をおすすめいたします! |
|
演習コースIII 「UX(User Experience)」 をおすすめいたします! |
|
演習コースIV 「セーフティ&セキュリティ」 をおすすめいたします! |
|
基礎コース 「ソフトウェア品質保証の基礎」 をおすすめいたします! |
| ○ 主査 | : | 田中 桂三(オムロン㈱) |
| ○ 副主査 | : | 白井 保隆(㈱東芝) |
| ○ アドバイザー | : | 中森 博晃(パナソニック コネクト㈱) |

田中氏
| 1. |
活動のねらい
ソフトウェア業界では、ソフトウェア品質向上の手段・手法として、これまでの経験より様々な品質管理やプロジェクト管理の方法が提案されています。しかし、これらが現状のソフトウェア開発プロセスに効果的に組み込まれているとは限りません。ソフトウェア品質の改善には、現実を見つめた品質とプロジェクトの管理方法の選定、および開発・保守プロセスへの適切な実装が必要不可欠です。 このような背景を踏まえ、本コースでは、問題解決をはかるために、開発と品質保証の現場に適応する対策方法を探求した上で、プロセス&品質モデル・メトリクス・先端技術等を活用してプロセスの定性的・定量的な分析・評価と組み合わせ、品質やプロジェクト・プロセスのパフォーマンス向上につながるよう、実践的に解決することを目的にしています。 また、参加メンバーが、ソフトウェアプロセスの研究を通じて、ソフトウェア技術者として幅広い知見と深い考察力を習得し、各組織に持ち帰ってさらに活躍されることを期待します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
各参加メンバーの課題を分析して、必要に応じて幾つかの研究テーマに分類し、テーマごとのグループが主体となって活動することを基本とします。希望に応じてプロセスや品質関連の規格・モデルの勉強会も開催します。 研究テーマとして、ソフトウェア開発や品質管理に関する「プロセス」の分析・評価・改善を通じて、「ソフトウェア品質向上」や「プロジェクト管理技術の強化」などに繋げることに取り組みます。 また参考になるプロセスや品質に関するモデル・概念や手法を選び適用して研究をすることもできます。例えば「プロセス改善モデルの効果的な活用」(CMMIⓇ、ISO/IEC 33000、ISO/IEC/IEEE 15288、ISO/IEC/IEEE 12207)[*1]、「品質特性による品質要求の分析と品質の評価・測定」ISO/IEC 25010(SQuaRE[*2]))、「プロジェクト管理手法の改善」(PMBOKⓇ[*3])、「DevOps[*4]) 他の国際規格・デファクトスタンダード・モデル・概念を参照して解決策に用いる、などです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他
[*1]:CMMI [*2]:ISO/IEC 25010 [*3]:PMBOK [*4]:DevOps |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 中谷 一樹(TIS㈱) |
| ○ 副主査 | : | 上田 裕之(㈱DTSインサイト) |
| ○ アドバイザー | : | 安達 賢二(Software Quasol) |

安達氏

上田氏

中谷氏
| 1. |
活動のねらい
レビューはソフトウェアの欠陥を早い段階で検出できる手段として、品質向上に寄与するだけでなく、コスト削減、納期短縮に効な手段と言われています。しかし、ソフトウェア開発の現場において、必ずしもその恩恵が受けられているとは言い難く、様々な悩みを抱えています。 本コースでは、レビューに関してメンバーやその組織が抱えている課題を共有し、その解決策について議論していきます。議論していく上で必要な知識やヒントとして、レビューに関する基礎知識、古典的技法や発展的技法、ならびに、実際の現場で効率的・効果的なレビューを行うための工夫・ノウハウ、個人のレビュースキルを向上させるためのテクニックなどを学びます。 そして、実際に演習で体験してそのやり方の良さや難しさを感じ取っていただき、自組織や自プロジェクトに適用しようとした場合に、どのような問題があるか、どんな工夫が必要かなどを考え、グループで議論していきます。 最近注目されている「生成AIの活用」が解決策の一つになるかもしれません。本コースでは、研究テーマの一つとして、生成AIの活用も積極的に検討していきます。生成AIは、あくまで選択肢の一つですが、希望する参加者にはこのテーマに基づいた具体的な方法を模索していく機会を提供します。 現場ですぐに役に立つレビュー方法、及び、レビューの歴史を変えるような画期的なレビュー方法の考案、この両方を研究の対象とすることに加え、生成AIの活用による新たなレビュー技術の開発など、最新のトレンドを踏まえた研究テーマも選択できるようにしています。 |
| 2. |
活動の進め方
|
| 3. |
その他
経験・知識の有無は問いません。 |
| ○ 主査 | : | 喜多 義弘(長崎県立大学) |
| ○ 副主査 | : | 秋山 浩一(㈱日本ウィルテックソリューション) |
| ○ アドバイザー | : | 西田 尚弘(㈱日新システムズ) |

喜多氏
| 1. |
活動のねらい
ソフトウェア開発の下流工程ではテストの自動化が進み、開発手法は従来のウォーターフォールからアジャイルへと進化しています。テストの環境は以前と比べて格段に良くなり、改善の余地があるところを探すのは徐々に難しくなってきています。 テストの目的を理解し、正しい知識を身に付け、テストの在り方についてまっすぐ向き合うことで、「実は今よりもっと良いテストが自分たちにもできるのでは?」と気づくことができるかもしれません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
本コースは、ソフトウェア工学の知見を入れた講義を通しながら、テストについての技法やノウハウについて研鑽し、研究していくコースです。新たな試みとしてコース内を研究に特化した「研究グループ」と演習に特化した「演習グループ」の2つに分け、研究コースと演習コースの両面を兼ね備えた内容を考えています。 具体的には、研究グループは従来と同様、テスト技法に関する講義からスタートし、研究テーマや課題を持ち寄り、その解決策などを研究し、最終的に論文を執筆するグループです。一方、演習グループは、テスト技法に関する講義からスタートし、演習を交えながらテスト技法の研鑽を行っていくグループです。 対象として、研究グループではテスト技法の知識を深めたい方や、日々のテスト業務の中で解決したい課題を持っている方を中心とし、研究を通して自身の知識や技術力を高めることを目指します。一方、演習グループではテスト技法の知識を深めたい方はもちろんのこと、テストに対して初学者や若手の方を対象とし、テストに対する正しい知識を身に着け、日々のテスト業務に活かしていくことを目指します。また、これらの活動を通して、各メンバーのテストの現場を改善するために必要な基礎力や課題解決能力の向上も目指します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他
コースの内容から、参加する方は例年、テストの現場経験が浅い方や若手の方が主ではありますが、ときには自己研鑽のためテスト技術を一から学び直したいベテランの方も参加されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 永田 敦(㈱日本総合研究所) |
| ○ 副主査 | : | 荻野 恒太郎(㈱カカクコム) |
| ○ アドバイザー | : | 山口 鉄平(㈱LayerX) |
| 1. |
活動のねらい
アジャイル開発のプラクティスを品質の観点からみていくと、よくできたソフトウェアエンジニアリングのフレームワークであることがわかります。 本コースの目的は、アジャイル開発に対して品質を中心に体系的にとらえ、現場にその真意を伝える工夫を研究して提案し、アジャイル によって得られる真の恩恵をチームと組織、そして顧客が享受できるようにすることです。 一方で、アジャイル開発は、その本質は変わらないものの、現場での実現は組織、ドメイン、製品、チームメンバーによって違い、実に多様になります。当然、そこから生まれる課題も多様なものになります。この研究会では、アジャイルの本質を認識しながら、違う経験のメンバーが、持ち寄った課題をまとめ、一つのテーマをチームとして議論し、仮説検証を行います。その学びが、それぞれの現場に価値をもたらすような研究を心がけます。 |
||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
コース運営もアジャイルを意識したフレームワークを考え、分科会活動の中でもアジャイルのプラクティショナー、スペシャリストを得 て、研究に厚みを加えます。
|
||||||||||||
| 3. |
その他
研究員の方は、原則としてアジャイル開発の現場をお持ちの方、または、これから持たれる方に限らせていただきます。アジャイルの手法は経験的プロセスで、実証的に積み上げられたものであり、ここでの研究も現場での実証をベースにしていきたいからです。 |
||||||||||||
| ○ 主査 | : | 石川 冬樹(国立情報学研究所) |
| ○ 副主査 | : | 徳本 晋(富士通㈱) |
| ○ アドバイザー | : | 栗田 太郎(フリー㈱) |

栗田氏

徳本氏

石川氏
| 1. |
活動のねらい
AI(人工知能)がプロダクト・サービスに組み込まれる機会が広がり、その品質保証は必要不可欠になっています(Quality for AI)。AIの品質保証においては、機械学習技術を用いデータから機能を導くという実装方式に起因する不確かさが高い一方、人間・社会に踏み込んだ品質、あるいは倫理・トラストまで追及することも求められます。このため、ステークホルダーとの対話から、テストの技法、運用・監視まで、従来のソフトウェアとは異なる原則や技術に踏み込み、固有の難しさに対処していくことが必要です。 一方で、従来ソフトウェアの品質保証においても、AIによる先進的な自動化技術を活用することで、様々な問題の解決につながる可能性 がります(AI for Quality)。データ駆動の機械学習技術の潮流だけにとらわれず、対象の問題を定式化し、機械学習、最適化、制約充足、論理的推論・検証といった様々な技術から適したものを選び使いこなすことが重要となります。 これらのテーマにおいて、対象となる「AI」も、教師あり学習により定型化されたタスクを扱うものから、GPT/ChatGPTをはじめとした大規模言語モデル・対話型生成AIにより非定型な入出力を扱えるものへと大きく広がりました。対話型生成AI自体の品質を扱うことも、対話型生成AIによる新しい品質技術のあり方を追及することも、喫緊の課題となっています。 本コースでは、Quality for AIおよびAI for Qualityの双方における価値創造や課題解決に挑んでいきます。いずれにおいても、非常に変化が速い先進的な技術を理解しつつ、まだ確立していない「品質のあり方」を議論し追及していくことが重要であり、本コースはそのための場を提供します。 |
| 2. |
活動の進め方
参加者の興味や問題意識について、講師陣からの最近の動向解説も交えながら全体で意見交換と議論を行います。その後大まかな方向性に基づいてグループ分けを行い、グループごとに具体的な研究テーマを定め取り組みます。 |
| ○ 主査 | : | 猪塚 修(横河ソリューションサービス㈱) |
| ○ 副主査 | : | 長谷川 裕一((同)Starlight&Storm) |
| ○ アドバイザー | : | 鷲﨑 弘宜 (早稲田大学/国立情報学研究所/ エクスモーション/人間環境大学/SI&C) |

鷲﨑氏

猪塚氏
| 1. |
活動のねらい
ソフトウェアやそれにより提供されるサービスに品質を組み入れて保証し続けるためには、企画や要求から保守に至るまでライフサイクルのあらゆる段階において、理論や経験に裏打ちされたソフトウェア工学技術の活用が欠かせません。本コースは1年間を通して、主要なソフトウェア工学技術の一通りを演習により深く体得する機会を提供します。 前提知識がないからと臆することはありません。ソフトウェア工学を一から学びたい方、現状のソフトウェア開発を改善したい方、スキルアップしたい方など、誰でもふるってご参加ください。 【本コースのポイント】
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール(2024年実績。2025年度は変更あり)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 柏原 一雄(㈱デンソークリエイト) |
| ○ 副主査 | : | 小池 利和(ヤマハ㈱) |
| ○ アドバイザー | : | 小室 睦(㈱プロセス分析ラボ) |

小室氏

小池氏

柏原氏
| 1. |
活動のねらい
演習コースⅡ「ソフトウェアメトリクス」は、ソフトウェア品質技術の1つの柱とも言えるメトリクスに特化したコースです。ソフトウェアの品質保証、プロセス改善、開発力向上のためにメトリクスを活用したい方を対象にしたコースです。 メトリクス測定、データのハンドリング、分析の各種手法を網羅的に習得していただきます。書籍「ソフトウェアメトリクス統計分析入門」に、実践→理論→考察→実践→・・・というスパイラルで、理解を深めていく有効な学び方が示されています。この考え方を参考に、本コースでは、手を動かす演習を重視しています。演習内容は、ほぼすべて講師の実践経験にもとづいたものであり、実践の疑似体験ができます。また、単なる詰め込み教育とはならないよう、学んだことを自身の職場で実践し、最終的にレポートとしてまとめることを目標にしています。 こうした、実践を重視するスタイルの本コースに参加することで、学んだ技術をすぐに現場で使える状態になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
メトリクス測定、データのハンドリング、分析の各種手法などを、講義だけでなく演習とディスカッションを交えながら学びます。 演習では、主にExcelを用いたデータ加工の方法やフリーの統計パッケージR、Rコマンダーを用いた統計手法などを習得します。講師の実践経験、研究員の実践経験を共有するディスカッションの場も用意し、研究員それぞれの課題解決の参考にしていただけます。分科会終了後(18:15~)に、飲食もしながらリラックスして、メンバー持ち回りで事例紹介をする「アフター」と呼ばれる活動も行います。 そして、講義・演習を通して習得したことを研究員のご自身の現場で実践していただき、コースの最後に「実践レポート」を作成していただきます。「実践レポート」作成に際しての困りごと等あれば、いつでも講師陣に相談をしていただけます。既に解決したい課題をお持ちで、関連するデータ収集もされているという場合には、解決策の個別指導のご要望にもお応えします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
※カリキュラムの順番, 開催月は変更される可能性があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
参考文献
[1]: 野中誠、小池利和、小室睦、『データ指向のソフトウェア品質マネジメント』、日科技連出版社、2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 金山 豊浩(㈱メンバーズ) |
| ○ 副主査 | : | 村上 和治(㈱SHIFT) |
| ○ アドバイザー | : | 三井 英樹(Weblysts.com) |

金山氏
| 1. |
活動のねらい
UX(User Experience)とは、製品やサービスを利用した際の「体験」を重視する設計思想で、利用者の目的や意向に沿って心地よく効率よく使えるように調査・設計・評価・開発を行うベースとなるものです。 本コースでは、UXに着目した研究を通して積み重ねてきた、企画品質や利用時品質を高めるノウハウ[*1]を演習形式で学び、ソフトウェア開発現場で実践できるように支援します。 「HCDコンピタンスマップ(2024年度)」を意識して、能力・技能・知識の向上を目指します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
全体を通して、UX手法の考え方や実践方法について座学、体験、ディスカッションにより学びます。 【実践するUX手法の例】[*3] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他(演習テーマ、注意事項、参考文献、本コースの目指すべき姿、理想像等)
[*1]
・SQiPライブラリ(UX関連文献): ・活動履歴: [*2]:ビジネスモデル2.0図鑑 [*3]:書籍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 金子 朋子(創価大学) |
| ○ 副主査 | : | 髙橋 雄志 (東日本国際大学/㈱日本AIシステムサービス) |
| ○ アドバイザー | : | 佐々木 良一(東京電機大学) |

佐々木氏

金子氏
| 1. |
活動のねらい
本コースでは、安全安心に関わる様々なテーマで講義を行い、演習やグループワークを通して深く技術を体得する機会を提供します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
事前学習や復習のための課題が出される場合があります。最終的に可能であれば、1年間の活動成果を論文としてまとめることを推奨しています。論文としてまとめない場合も、成果報告書は研究員の皆さまで作成していただきます。セーフティやセキュリティに関する特別な知識や経験は必要ありませんが、現場における問題意識をお持ちの方を歓迎します。情報セキュリティを学びたい方、異なる分野のセーフティを知りたい方など、どなたでも参加可能です。 様々な分野の外部講師をお招きし、最新の技術動向やトピックを提供しますので、継続的な参加を歓迎します。もちろん、単年受講の方も歓迎します。 分科会活動のない月(9月)や、テーマに近いトピックを扱うシンポジウムへの参加推奨、成果報告書をまとめる段階など、適宜(年間で2から5回程度)、臨時会を開催します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他(演習テーマ、注意事項、参考文献、本コースの目指すべき姿、理想像等)
本コースでは、コースの立ち上げから3年間の成果中心とした内容を『セーフティ&セキュリティ入門~AI、IoT時代のシステム安全』としてまとめ、日科技連出版より発刊しました。このノウハウを活かし、最先端の技術を用いた演習・研究に取り組みます。最終成果をSQiPシンポジウムなどの外部発表に発展させることを推奨しております。 演習でツールを使用するケースもあるため、作業用のPCをご用意いただけますと演習にスムーズに参加いただけます。 最終成果を論文化する場合には、問題提起から問題解決に至るロジックを相手に伝えるテクニックも身に着けられるようにサポートいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 主査 | : | 岩井 慎一(㈱デンソー) |
| ○ 副主査 | : | 土屋 治世(SCSK㈱) |
| ○ アドバイザー | : | 飯泉 紀子(丞コンサルティング㈱) |

飯泉氏

土屋氏

岩井氏
| 1. |
活動のねらい
ソフトウェアの品質保証に新たに取り組まれる方、改善や改革を目指している方を対象に「ソフトウェア品質保証の基礎」を習得することをねらいとしています。実務経験豊かな指導講師による講義と、講師とメンバー及びメンバー同士のディスカッションを通じて、考える力を身につけ、自分自身のスキルとすることを目指します。 本コースを足掛かりに、翌年以降、他コースへ参加するメンバーも多数おり、SQiP研究会の入門コースとしても位置づけられています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. |
活動の進め方
各回、前半は講義、後半はグループディスカッションを実施します。 前半の講義では、ソフトウェア品質保証の基礎技術について、当該技術の専門家による講義を行います。講義の中では、必要に応じて演習も行います。講義のテーマは、『ソフトウェア品質知識体系ガイド–SQuBOK®Guide–』の知識領域の多くをカバーしています。 後半のグループディスカッションでは、各回の講義テーマについて、他の企業のメンバーとのディスカッションを通じて、自社の改善に役立つ情報や知見を交換します。また、当該テーマに関する問題点と改善提言をまとめます。 本コースは例会に加えて、2回の特別例会を実施します。 原則、日科技連(東高円寺)に集合して実施します。やむを得ず日科技連に来ることができない場合はリモート参加も可能ですので、主査に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. |
年間スケジュール
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |
その他
本コースでは論文作成はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||