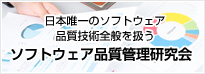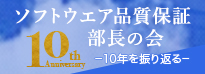| 特別講義レポート: | 2024年 | 過去のテーマ: | 一覧 |
| 例会 回数 |
例会開催日 | 活動内容 | |||||||||
| 2023年 | |||||||||||
| 1 | 5月19日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 2 | 6月23日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 5 | 10月13日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 6 | 11月10日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 7 | 12月8日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 2024年 | |||||||||||
| 8 | 1月26日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 日時 | 2023年10月13日(金)9:50 ~ 12:00 |
| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 *ハイブリッド開催 |
| テーマ | 国際共通語としての日本文/英文ライティングを目指す — 英語を見ると日本語が見えてくる |
| 講師名・所属 | 中村 哲三 氏(株式会社エレクトロスイスジャパン) |
| 司会 | 栗田 太郎 氏(ソニー株式会社) |
| アジェンダ |
ビジネス文の書き方は英語と日本語で異なる? — テクニカルライティング
|
| アブストラクト |
ライティングは、あらゆる分野の土台になる基礎技術です。たとえ、研究成果が優れていても、その優れた点をライティングで読者に伝えきれなければ、読者から認めてもらえません。あなたの研究成果が全世界の読者に適切に伝わるように日本文や英文を書く必要があります。そのためには、英語の特徴を活かして日本語を書くことを心がけ、日本文も含めて国際共通語として伝わるようなライティングを心がけます。まず英語と日本語の概念の違いなど言葉の問題を整理して、英文と日本文のテクニカルライティング力を身につけましょう。 |
| 講義の要約 | |
|
第5回の特別講義では、「国際共通語としての日本文/英文ライティングを目指す」と題して、中村氏よりご講義をいただきました。説得力がある文章を書くため必要な知識として、英語と日本語の違いについて説明いただき、その違いを踏まえた上で、英文の論理構成を活用するというライティング技法について講演をいただきました。 冒頭、中村氏より自己紹介が有りました。
<ライティングで注意すべき点>
日本文と英文の違いを意識する — 文に含まれる情報量の違い
概念の違いから生じるコミュニケーションギャップ
社会に氾濫するカタカナ語 = ほぼ和製英語(動詞も含む)
専門用語を使いこなすことで生じる問題
思いがけないところで生じる差別表現
一定した視点で書く
わかりやすく、翻訳しやすい日本語を考える
これまで学習したことがなかった句読法や表記法
<ビジネス文の書き方は英語と日本語で異なる? — テクニカルライティング>
ビジネス文
新常態でこそ問われる論理性
テクニカルライティング
パラグラフとは
パラグラフと文章
パラグラフライティング
パラグラフの論理構成 ライティングツールを活用する
情報を論理的に整理する(パラレリズム)
漢字とかなの書き分け
遷移語(接続語)
行為は動詞で表現するー行為を名詞化しない
行為の名詞化は冗長でもったいぶったお役所言葉
必須情報と随意情報をわける
説明する順序に注意する
修飾関係を明示して、複数の解釈ができないようにする
トピック志向とタスク志向ー何を主語(視点)にするかという問題
国際共通語としての英語
Amazonで「英文テクニカルライティング72の鉄則」を検索してください
(講義の感想)
今回の講義は品質管理という分野に限らず、「相手に伝わる文章の書き方」について、英文の構造を参考にしながら、わかりやすく講義いただきました。個人的に英語を学習していますが、「言われてみると確かにそうだな」という内容が多く、今後の論文作成にも即活用できるエッセンスが多く含まれていました。また、普段英語を学習していない方にも、とてもわかりやすく、説得力がある講義でした。ご紹介いただいた「英文テクニカルライティング72の鉄則」については、是非読んでみたいと思います。 |
|
| 日時 | 2023年11月10日(金)9:50 ~ 12:00 |
| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 *ハイブリッド開催 |
| テーマ | 自動運転、高度運転支援時代の車載ソフトウェア開発と品質評価 |
| 講師名・所属 | 森崎 修司 氏(名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授) |
| 司会 | 岩井 慎一 氏(株式会社デンソー) |
| アジェンダ |
利用環境や利用範囲をより明確にした上での開発と品質評価
より広範囲な要素技術
新しいタイプの欠陥
ソフトウェア開発と品質評価で考慮すべきこと
|
| アブストラクト |
より高度なセキュリティの実現、自動運転や高度運転支援への対応といった車載ソフトウェアへの要求に対応するため、センサ/カメラやそれらの組合せアルゴリズム、OTA(Over The Air: 無線通信によるソフトウェアの更新、変更)、車外サービス連携、ODD(Operational Design Domain: 運行設計領域)といった要素技術や基盤の整備が進んでいる。車載ソフトウェアの開発や品質保証もそれらに合わせて変えていかなければならない部分がある。本セッションでは、そうした車載ソフトウェアをとりまく新たな環境や要素技術を整理する。その上で、これからの開発や品質保証に求められる変化をソフトウェアエンジニアリングの観点から解説する。また、講演者らの研究グループで検討している研究テーマを紹介する。 |
| 講義の要約 | |
|
第6回の特別講義では、「自動運転、高度運転支援時代の車載ソフトウェア開発と品質評価」と題して、森崎氏よりご講義をいただきました。 冒頭、森崎氏より自己紹介が有りました。
アウトライン
本講演で考えていただきたいこと
自動運転/高度運転支援の分類と大まかな仕組み
利用環境や利用範囲を想定した開発と品質評価の必要性
新しいタイプの欠陥
ソフトウェア開発プロセスと品質評価としてそのほかに考えるべき点
私の研究グループでの研究テーマ
(講義の感想)
|
|
| 日時 | 2023年12月8日(金)9:50 ~ 12:00 |
| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 *ハイブリッド開催 |
| テーマ | AIによって変わる品質保証の考え方 |
| 講師名・所属 | 徳本 晋 氏(富士通株式会社 富士通研究所 シニアリサーチマネージャー/本研究会 指導講師) |
| 司会 | 栗田 太郎 氏(ソニー株式会社) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト |
近年、人工知能(AI)の社会実装が進められており、AIの社会への影響がますます大きくなっているが、従来システムとは異なる特性を持つAIに対する品質保証についてはまだ十分にプラクティスが蓄積されておらず、大きな課題の1つとなっている。また(従来システムも含めた)品質保証技術についてもAIを用いることで高度化してきており、AIは品質保証にとって影響力を無視できないものになってきている。 |
| 講義の要約 | |
|
第7回例会の特別講義では、「AIによって変わる品質保証の考え方」と題して、徳本氏よりご講義をいただきました。 冒頭、徳本講師より自己紹介が有りました。
講演の流れ
はじめに(本講演の「人工知能 (AI)」の範囲 )
本講演で扱うのは、下記3点のうち、2点目・3点目である
AIシステムの課題
◆AIのためのソフトウェア工学
大規模言語モデルで変わるソフトウェア工学
おわりに
講義の感想
今回の講義は、AIに対する品質保証、AIによる品質保証に関して、最新の動向を踏まえた講義をしていただきました。講義内容が非常に高度なものであり、難しい内容も多くありましたが、実例を用いてわかりやすく説明していただき、とても参考になりました。特にChatGPTの活用に関する注意点や限界についてもコメントいただき、とても納得感が得られました。 |
|