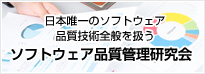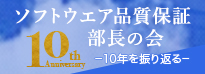| 特別講義レポート: | 2024年 | 過去のテーマ: | 一覧 |
| 例会 回数 |
例会開催日 | 活動内容 | |||||||||
| 2021年 | |||||||||||
| 1 | 5月21日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 2 | 6月25日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 3 | 10月8日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 4 | 11月12日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 5 | 12月10日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 2022年 | |||||||||||
| 6 | 1月7日(金) |
特別講義
|
|||||||||
| 日時 | 2021年5月21日(金)10:00 ~ 12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | ソフトウェア開発の真のボトルネックとは何か? |
| 講師名・所属 | 岸良 裕司 氏(Goldratt Japan CEO) |
| 司会 | 岩井 慎一 氏(株式会社デンソー/本研究会 基礎コース 主査) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト |
ソフトウェアが産業界のボトルネックになりつつあり、一部には開発プロジェクトの破綻のせいで経営危機に陥る会社も出てきています。今回のセミナーではソフトウェア開発における真の制約とは何かを明らかにし、そこに取り組むことで、目覚ましい成果を出すシンプルなロジックと事例をご紹介します。 特別な準備はいりません。組織を良くしたい。プロジェクトを良くしたいという思いだけ持ってきていただければ結構です。講義はわかりやすく実践的にしていきます。 |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介 岸良 裕司(Goldratt Japan CEO) <略歴> 1.はじめに
2.全体最適のマネジメント理論
3.流れがすべて~シンプル化に向けた取組み
4.まとめ
変えられない過去から、変えられる未来に!マネジメントが変われば、現場が変わる。 5.質疑応答
<質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> |
|
| 日時 | 2021年6月25日(金)10:00~12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | ユーザーモデルを活用したコミュニケーションの理論と実践 人の“気持ち”を知るためのユーザーモデルの考え方 |
| 講師名・所属 | 小澤 一志 氏(ユーザーモデリングラボ代表) |
| 司会 | 金山 豊浩 氏(株式会社メンバーズ/本研究会 演習コースⅢ 主査) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト |
企業にとって、お客さまと有効なコミュニケーションを取ろうとするならば、お客さまをよく知ることは最も重要なことであり、ビジネスの形式がB2Cであれ、B2Bであれ、コミュニケーションの主体が“人”であることも基本的には変わりはありません。 |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介 富士ゼロックスの研究開発部門を退職後、心理統計(多変量解析)・認知工学をベースとしたインサイトモデル(ユーザーモデル・心理モデル)及びCX/UXの評価方法の研究に取り組みながら、これらの技術や研究成果を活用したサービス事業の開発支援やコンサルティングを行うための場とすべく、「ユーザーモデリングラボ」を起業。 1.ユーザーモデルとは
2.ユーザーモデルの着眼点
3.ユーザーモデルを作るためのステップ
4.ユーザーモデルを活用するために
5.ユーザーモデルの活用事例
6.まとめ
ユーザーモデルは、人が様々な対象に対してもつ心理特性に基づいて、人の“気持ち”の解像度を上げるために作られるものである。その適用範囲は非常に広く、事例の中で紹介したように、活用もアイデア次第で広がっていく。 7.質疑応答
<質問> <回答> |
|
| 日時 | 2021年10月8日(金)10:00~12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | パタンと品質 |
| 講師名・所属 | 原田 騎郎 氏(株式会社アトラクタ Founder 兼 CEO) |
| 司会 | 永田 敦 氏(サイボウズ株式会社/本研究会 研究コース4 主査) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト | |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介 原田 騎郎(株式会社アトラクタ Founder 兼 CEO) アジャイルコーチ、ドメインモデラ、サプライチェーンコンサルタント。 1.パタン(パターン)とは何か?
2.ソフトウェア開発におけるパタンの活用
大規模開発が広がる中で、ソフトウェアにもパターンを適用することができないか考えられるようになった。初期の段階では、ケント・ベックやウォード・カニンガムらがWikiWikiWebというWEBサイトで、ソフトウェア開発においてうまくいった話をドキュメント化し、共有した。また、PLoP(パターンについて話し合う活動)が行われるようになり、様々な成功したパターンが集められるようになった。
3.スクラムによる開発での適用の試み
4.品質保証からアジャイル品質への変化
5.まとめ
ユーザーにとってよいプロダクトとなるパターンを書き、集めることが今後の展望。 6.質疑応答
<質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> | |
| 日時 | 2021年11月12日(金)10:00~12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | プロダクトライン開発の考え方-共通性を確立して可変性を確保する |
| 講師名・所属 | 林 好一 氏(Y’s Workshop 代表 兼 ソフトウェアプロセスエキスパート) |
| 司会 | 岩井 慎一 氏(株式会社デンソー/本研究会 基礎コース 主査) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト |
プロダクトライン開発(PLE)とは、広義の派生開発であり、共通性を持つ複数のシステムを視野に入れる開発方法である。単品開発とは異なり、再利用を強く意識する。そのため、複数システム間の共通性を識別する。他方、システムごとに異なる点は可変性として識別し、各システムで追加変更削除が可能になる仕組みを設ける。 |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介
林 好一 氏 <略歴> 研究論文や著書 その他(学位、表彰、学会活動) 1.プロダクトライン開発とは?
2.共通性と可変性
3.どうやってプロダクトライン開発をすすめるのか
4.コア資産をフィーチャモデルで表す
5.プロダクトライン開発のプロセス
6.オススメのプロダクトライン開発の進め方
7.質疑応答
<質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> | |
| 日時 | 2021年12月10日(金)10:00~12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | システム視点からの信頼性と人の思い込みのリスク |
| 講師名・所属 | 田中 健次 氏(国立大学法人電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授) |
| 司会 | 平山 照起(一般財団法人日本科学技術連盟) |
| アジェンダ |
|
| アブストラクト |
システムの信頼性を考えるとき、対象となるシステムのみを隔離・抽出して信頼性を評価することはできない。設計者・運用者・ユーザーなど関わる多くの人との関係、さらに他のシステムとの繋がりなど、多様な要素が関連する中で現実の状況を予測する必要がある。複数エージェントが絡むシステムの信頼性を脅かす問題がどこに存在するのか、特に人の活動や知識がもたらす問題に着目し、考えてみたい。 |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介
田中 健次 氏 <略歴> 1.はじめに
2.モノとモノの関連から信頼性を視る
3.人とモノとの関連から
4.人と人との関連から 意図のずれ
5.ダブルチェックの効果
6.質疑応答
<質問>
<回答>
<質問>
<回答>
<質問>
<回答>
<質問>
<回答>
| |
| 日時 | 2022年1月7日(金)10:00~12:00 |
| 実施形態 | オンライン(Zoom)開催 |
| テーマ | 機械学習品質マネジメントガイドライン策定と標準化の取り組み |
| 講師名・所属 | 大岩 寛 氏(産業技術総合研究所 デジタルアーキテクチャ研究センター副研究センター長) |
| 司会 | 石川 冬樹 氏(国立情報学研究所/本研究会 研究コース5 主査) |
| アジェンダ |
1. 背景 |
| アブストラクト |
機械学習AIを用いたシステムが広く世の中で使われるようになっていくなかで、システムの信頼性や安全性を担保するための品質マネジメントの必要性が生じてきている。現在産学協同の取り組みで検討している機械学習品質マネジメントガイドラインの策定について、その背景となる世界の状況や品質管理の考え方、標準化の状況などについて紹介する。 |
| 講義の要約 | |
|
◆ 講師紹介 2005年3月:東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。 1.導入・背景
2.機械学習品質マネジメントガイドライン
機械学習AIの品質を「作りこみ」「確認し」「説明する」ためのガイドライン。
3.国際標準化
4.今後の取り組み
5.まとめ
機械学習の品質は作りこむだけでなく、確認し、説明することも大事である。それを目指すために機械学習品質マネジメントガイドラインを提供している。ガイドラインは、ソフトウェアを作る人だけに使われるのではなく、社会全体でAIを安心して使ってもらうための基準や認証の基盤としての利用も期待している。 6.質疑応答
<質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> <質問> <回答> | |