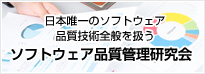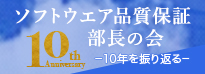「ソフトウェア品質保証プロフェッショナルの会」からの発表
参加者は前回とほぼ同様の95社、152名と多くの方に参加いただきました。チームの成果発表では昨年よりも1チーム多い6つのチームが発表を行いました。昨今のAIブームを受けて今回も生成AIを使った品質保証に関する発表が2件ありました。そのほか、サービス品質に関する発表、30年後の品質保証についての発表、「情緒的品質」についての発表と、多彩な発表がありました。また、昨年発刊した「ソフトウェア品質保証の極意」の普及活動として、講演会や勉強会を実施しているという発表もありました。講演にはソフトウェア品質保証プロフェッショナルの会のアドバイザをお願いしている、名古屋大学の森崎先生から「費用対効果の高い品質保証にむけて」というタイトルで講演をいただきました。
なお、今回発表した中の2件については、9月に開催される「ソフトウェア品質シンポジウム2025」で最終発表を行います。成果発表会に参加いただけなかった方は、ぜひ、この機会に参加ください。
| 日 時 | 2025年7月23日(水)13:30~17:50 |
| 配信会場 | 一般財団法人日本科学技術連盟 東高円寺ビル |
| 実施形態 | オンライン開催(Zoom) |
| 時間 | 内 容 |
| 13:30~13:35 | 主催者挨拶 平山 照起(一般財団法人日本科学技術連盟 品質経営推進センター 品質経営・SQiP・MS・QCCグループ 係長) |
| 13:35~13:45 | 活動の紹介 鎌倉 洋一 氏(源氏企画(元富士通株式会社) |
| 13:45~14:10 |
成果発表1 過去の問題を繰り返さないための生成AI活用検討 ~生成AIを活用した本質的再発防止の検討支援~ チーム2 横尾 清吉 氏(株式会社 富士通ゼネラル)発表概要 重大な不具合が発生した際、なぜなぜ分析などを通じて原因を特定し、チェックリストの整備やプロセス改善といった再発防止策を講じる取り組みは一般的に行われています。しかしながら、実際には同様の問題が繰り返し発生してしまうケースも少なくなく、その一因として、限られた工数や再発防止に関する知見の不足により、問題の本質に十分に迫り切れていないことが挙げられます。 |
| 14:10~14:35 |
成果発表2 生成AIを活用したリスクマネージメント チーム6 深水 廉子 氏(SCSK株式会社)発表概要 昨年度は、「高品質なソフトウェアやシステムを開発・提供し続けられる組織」へと成長させるために、ノウハウの有効活用によって組織全体の技術力向上と過去の失敗の再発防止を目指し、生成AIの適用可能性を検証する活動を行いました。 |
| 14:35~14:45 | 休 憩 |
| 14:45~15:10 |
成果発表3 サービス品質と品証部門との関わり方 チーム3 大塚 俊章 氏(BIPROGY株式会社)発表概要 サービス開発(コトづくり)において、これまでのモノづくりとは異なる観点で考えなければならないことがある。モノづくりがこれまでの顧客に納品して完了となる開発スタイルに対して、コトづくりは作ったサービスを運用し続けることが前提となる。 |
| 15:10~15:35 |
成果発表4 30年後を見据えて未来の品質保証の再定義 チーム5 風見 玲衣 氏(株式会社JCHunter)発表概要 生成AIの登場により今後のソフトウェア品質保証の在り方ややり方など大きな変化が想定される。 |
| 15:35~16:00 |
成果発表5 AI活用時代だからこそ大事にしたい『ソフトウェア品質保証の極意』の普及 チーム4 小島 嘉津江 氏(1FINITY株式会社)発表概要 生成AIなどに象徴される急速な技術進展の中、ソフトウェア品質の確保がますます難しくなっています。どのようなアプローチが有効か、どのような場合に成果が得られにくいか、どのようにすれば品質保証活動を定着させることができるか。このような現場の悩みを解決する手がかりとして、品質保証部長の実践的な知見や品質への想いを込めた書籍『ソフトウェア品質保証の極意』を2024年9月に発刊しました。 |
| 16:00~16:10 | 休 憩 |
| 16:10~16:35 |
成果発表6 情緒的品質の定義とその理解の提案 チーム1 島貫 さやか 氏(株式会社システムインテグレータ)発表概要 2023年度に提案したCXQ(顧客体験品質)を基に、マーケティング理論における製品・サービス品質とISO/IEC25010:2011で定義されるソフトウェア品質の境界に着目し、「情緒的品質」という新しい概念を提唱する。 |
| 16:35~17:35 |
講演 費用対効果の高い品質保証にむけて 森崎 修司 氏(名古屋大学)発表概要 費用対効果の高い品質保証の方策として次の2つを紹介します。1つはバグや問題のタイプの見極めとタイプ別の検出手法を選ぶことです。もう1つはユーザー像を想定することにより、より適切なユーザー価値を提供できるようにすることです。 |
| 17:35~17:45 |
日科技連からのお知らせ 日科技連の事業紹介 平山 照起(一般財団法人日本科学技術連盟 品質経営推進センター 品質経営・SQiP・MS・QCCグループ 係長) |
| 17:45~17:50 | クロージング 川田 葉子 氏(元株式会社構造計画研究所) |